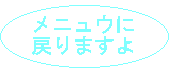�@8��7���i���j�̋L��
�@���[�ɂ���
�@���ߏ��ł́w���[�Ղ�x���s���Ă���Ƃ�����l��
�Ƃ̌���ɍ��|�ɒZ���������Ă������B
���N�O�i�q���B���������������j�܂ł�
�䂪�Ƃł��w���[���܁x������A�Z�����|�\�������������̂�
�c�ŁA�w���Ȃ��x�͂V���V���ł��B
�Ƃ��낪����́w�V���V���x����̘b�Ō��݂ɂ����Ă�
�w�W���V���x�̏��������A�����炪��ʓI�c�ł���
���N�́w����V���V���x�͂W���P�P���ŁA���N�ς��
�w���Ȃ��x���A����₷�����x��́w�V���x�ɒ�߂Ă���悤���B
�������V���̒��ɂ����Ắw���Ձx�Ɖ]���w�V���̖�x�̂��Ղ�ł͖����悤�ł�
�@�~�̓���ɂ���
�~����Łw�ӉZ�̔n�x���w�֎q�̋��x�����܂��������m�ł��傤���H
���̈Ӗ���
����c�l���}���̉��ɓ�����A�����Ƃɖ߂��ė����悤�n�ɏ��
�~���I���Ƒ���Ƌ��ɂ������A��悤���ɏ��@�ƌ����Ӗ��ł�
�����Ĥ�w�@�̗t�x�͐����ł��Ȃ��������@�̗t�ɏ悹�Ă��̐��֑���̂������ł�
�@������q�̍l����
�@�m�g�j����e���r�Łw�����Ă̒��̒��x���A�G�ɂ�������ŏ��w���R�O�l�̓�
���Ă���h�����̂��P�T�l�B�R���͕��͂ǂ���
������h�����̂��T�l�B������́w���x�ň�x���͂�����́w���x�ɕt���Ă���
�����Ă̗�����h�����̂��P�O�l�B
������I�P�O�l�́w�ǂ�����w���Ă��邩����Ȃ����痼���x�Ɠ������ƌ����B
�����I�ɑI�P�T�l�B�z���͖L���ȂT�l�B�����ė\�������Ȃ�(���ɂ�)�P�O�l�B
���̌��ʁA�M���͂ǂ��l����H
�@�䕗�̗\���m��
����́w�P�P���x�̓}�[���[
���{�ꂽ�w�P�Q���x�̓O�`�����Ɩ��t�����Ă���
���ɑ䕗����������Ɓw�^�����x�ƂȂ�炵��
����́w�A�W�A���x�Ƃ��ċL�^����Ă���
�@�����̈ꕔ
�@�����ł́i�g�c�n���̎��̎���ł́j�Â�����
�w�R�^�c�x��w�����x�Ȃ�
���g���g�[���ʼn��܂�Ƃ���
�w�ʂ���ׁ`�x���ƌ���������g��
���Ƃ��q�l�́A�����ĂȂ���
�w���������A�Ƃڂ��ɂ������Ăˁ`�ŁA�������Ƃ���ȁx
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʖ�u���������A���ւɗ����Ă��Ȃ��ŁA�����ĉ������v
�w�O�͊���������ׁH���������A���������Ăʂ���ׂɂ������Ƃ���ȁx
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʖ�u�O�͊��������ł��傤?������ʼn��܂��ĉ������v
���ƁA�����悤�ȋ��
���́w�ʂ���ׁ`�x�́A�O��̕��͂Łw�ʂ���ׁx�ɂ��Ȃ�
�@�ފ݉Ԃɂ���
�@���̕ӂł͓����s�̋В��c���ό��X�|�b�g�ɂȂ��Ă��܂�
���낻��A������ɂȂ�̂ł́c
���ɂ��܂��Ƥ���N����L���i��200�j�������ł��I
�R�m�w�ފ݉ԁx(�H�ފ݂̍��ɊJ�Ԃ���̂�)
�ʖ��w�֎�щx(�V��̉Ԃ̈�)
�ƌĂ�Ă���̂͂����m�ł��傤
�w�ʖ��x���ꂪ�A�r�b�N��!!
�ȁE�ȁE�Ȃ�Ɓw�P�O�X�O�x���̌Ăі������邻���Ȃ̂ł�
(1090�̂قƂ�ǂ������j
�����q���̍��Ɂw�ׂ낫��ȁx�ƌĂ�ł��܂���
�q���S�ɂȂ�Ƃ��C���̈������O���Ȃ��Ǝv�������̂ł�
�y�ʖ��̈ꕔ�z
�w�t�����Ԍ����x�i�ԂƗt�����Ɍ����Ȃ�����j
�w�ωԁx��w�ς��x��w�ς̏����i�����܂j�x
�w��Ȃ���x�E�w���l�ԁx��w�����ԁx��w�n���ԁx��w���U�ԁx
�w�ǂ�ǂ낯�ԁx�i�ǂ�ǂ낯�͒��挧�̕����ŗ��j
�w�h�N�o�i�x�i���̕����Ƀ��R�����Ƃ����ł�����c���A
�̂̐l�̓R�����ꒋ��ȏ㗬���ŁA���炵
������ł����Q��̎��ɂ��Ȃǂɂ��ĐH�����j
�@�H�����ɂ���
�@�H�����͒n�����ƌ����̂����邻���ŁA
��Ɂw�T�C���x�Ƒ��ɃT�G���A�T�����A�T�G���A�Z�C����������B
�T���}�͎��b�^���p�N���r�^�~���~�l�����𑽂��܂�
DHA(�h�R�T�w�L�T�G���_)�EEPA(�G�C�R�T�y���^�G�C�_)�E�r�^�~��A�E�r�^�~��B12�E�i�C�A�V���Ȃǂ�
�h�{�f���܂�ł��܂��B
�T���}�̓����ɂ́A�w�r�^�~��A�x���L�x�Ɋ܂܂�Ă���̂ł��B
����ɁA�r�^�~��B1�E2�EC�A�i�C�A�V�����܂܂�Ă��܂��B
�T���}�̍��ɂ��J���V�E�����͂��߃~�l�����A�r�^�~���Ȃǂ��܂܂�Ă����ł��B
�T���}�͉�V���Ȃ̂Ő��������ɐ�������̂ō������̋��ɔ�ׂď_�炩���B
�w�H�����x�͎��̂��Ƃ��w�H�̂����x�Ȃ̂ł���
���̔N�́w���Q�x�ׂ�D���A�U�������ɏo�����Ď������Ƃ�
����ŕ߂ꂽ�H�������A�V�[�Y���̈�Ԃ͂��߂̂V���̏��{���璆�{���炢�ɏo���̂ł��B
�ƌ������ƂŁA�w�H�̂����x�̏H�����͐^�Ăɓ���O�Ɏp������킷�̂ł��B
���݂ɁA�����D�ł̋��l�́w�h���ԁx
���ʂ́w�H�����_��ԁx�Ƃ������@�B
���́w�H�����_��ԁx�͓��ɋ߂Â��H�����̏K���𗘗p�������@�ŁA
�H��������Q�ƂȂ��ďW�܂��Ă��邽�߁A�H������������ł��܂���
�w�h���ԁx�͖Ԃ����Ƃ���ɗ����H�������������l����̂�
�O���́w�����x���������H�����̂悤�ł��B
�@��
�w�c����x
�@�č��͏t�̖K��ƂƂ��ɖZ�����Ȃ�܂�
�S�����ɂȂ�ƕc�Â��肪�n�܂�܂�
�y���������c���̒��ɏ��ł��ꐅ���z�킹������݂��܂���
���̏�ɔ����y�����Ԃ����܂��B
�����āA�r�j�[���n�E�X�̒��ɂ�����ƕ��ׂ�ꔭ�肷��̂�҂��܂�
�w�c�N�����x
�@�c��ڂɊ��[���Ƃ���]�Ƃ�����엿���܂��A�g���N�^�[�ōk���܂�
�̂͐l���������g������A����n�œc��ڂ��k���Ă��܂���
�w�ォ���x
�@�c�N�������I���Ɠc�ɗp���H���琅�������c��ɂ���ォ�������܂�
�w�c�A���x
�@�T�����ɂȂ�ƁA�c�A�@���g���ēc�A�����n�܂�܂�
�@�B�ŐA�����Ȃ��c�̋��̕��͕�A[�ق��傭]�Ƃ����Ď�ŐA���܂�
�w�엿�A�����x
�@�c�A�����I����Ă���͋C����̐L�ы���݂�
����엿�̒��߂�������A���������Ȃ��悤�ɏ����܂��܂�����c
�����c���傫���Ȃ�悤�Ɂw�厖�Ɂx��Ă܂�
�~�J�̍��ɂȂ�ƈ�̂��Ԃ��傫���Ȃ�A����ǂ�ǂ�L�юn�߂܂�
��̈ꐶ�ň�ԑ厖�Ȏ��́A�Ăɕ䂪�ł���V�����ƁA�䂪�ł�W�����ł�
���̍��ɕa�C��Q����������邽�߂ɔ_����܂����肵�܂�
�䂪�ł���V�����ɒႢ���x�̓��������ƁA��Q�ɂȂ�傫�Ȕ�Q���܂�
�X�����ɂȂ�ƈ�̕䂪���艩���F�ɂȂ�܂�(���̕ӂɂ�[��]�A[��]���c)
�w���x
�@��͑�^�R���o�C�����Ō��錩�邤���Ɋ������܂�
���̌�A������ꂽ���݂́w�k�^�@�x�ȂǂŔ_�ɂ։^�꒙������܂�
�w�����x
�@��������A�ቷ�Œ�������܂�
�����ĕK�v�ȂƂ��ɕK�v�ȗʂ����A�����肳��܂�
�@��CM�\���O
�P�X�T�P�N�A���W�I�����œ��{���́w�b�l�\���O�x���g�����b�l���I���G�A���ꂽ������
�����Z�i���݂̃R�j�J�j�́u������t�B�����v�̐�`�̂��߂ɂ���ꂽ�b�l�\���O�̃^�C�g����
�w�l�̓A�}�`���A�J�����}���x�̂̂Ȃ��ɎЖ��E���i���͓����Ă��Ȃ����̂�
�e���݂₷���̎��ƃ����f�B�ł����܂������̊ԂɐZ�����Ă�����
���̂b�l�̐����ɂ���ă��W�I��e���r�ł́A���b�l�\���O�u�[�����K���̂����A
����Ȃb�l�\���O�S�������x�����̂�
�u�l�̓A�}�`���A�J�����}���v�̍쎌�E��Ȏ҂ł�����O�،{�Y
�u���邢�i�V���i���v��u�|�|���E�|�|���v����ɂ́u�������3��3���v�ȂǁA
���ł��L���Ɏc��悤�Ȃb�l�\���O�𐔑����肪���Ă���
���݂Ɂw�S�l28���x���ꂩ��w�W�����O�����x�̃e�[�}�\���O�����̐l
���܂ł��L���Ɏc��A�q�ǂ��������������ނb�l�\���O��
����ɂ����āw���w�x���d�v�ȈӖ��������Ă���̂�������Ȃ�
�@�����Ɖ��ɂ���
�����̌����́A���Ƃ����сA�Ă��ł��B
�����̓����ͤ�Ö������邾���łȂ��A
�����炩�������褗��Ă����ӂ����炳������A�J�r��ۂ�h�����ʂ��L��܂��B
�����́A�����̑傫�����Ԃ̈Ⴂ�ɂ���āA
�O���j���[����㔒��������瓜��O������������Ȃǂ�����܂����A
�������ӊO�͖��ɑ傫�ȍ��͊������܂���B
�����̏��x�̈Ⴂ�Ŗ��킢���Ⴄ�Ƃ���Ă��܂��B
���x�̍������F�̍����͒W���ȊÖ��
���x�̒Ⴂ���n�F�̍����͊Ö���������s�������܂ނ��ߓƓ��̃R�N������܂��B
�@�w�����������x
�����̖��t���͍��������|�E�ݖ�����X�̏��ł��B
������������ɓ����̂ͤ
���q�̏������ݖ��̉�������ɓ����Ă��܂��Ƥ���q�̑傫�����������ݍ��܂Ȃ��Ȃ邩��ł��B
�@�w���x
���̌����ͤ�≖��V�R����C���ł��B
���ɂͤ�f�ޒ��̐������O�ɏo������A��Ȃǂ̊��F�h�~�
�����Ȃǂ̃k�������A����ς����̋Ìō�p�Ȃǂ̌��ʂ��L��܂��B
�܂�����Ђ��≖���ȂǐH�i�̉��H��ۑ��ɂ��g���܂��B
�p�X�^��䥂ł鎞���������̂ͤ�����������̂���ς����ɓ��������
����ς����̎听���ł���O���e���̔S����o�����������߂Ĥ�p�X�^�̃R�V�����߂邩��ł��B
�@���̕�ɂ���
 ���̐A���͐��ӂ���n�ɐ�����w���̕�x�ł��B
���̐A���͐��ӂ���n�ɐ�����w���̕�x�ł��B
�̘b�w�����̔��e�x�ʼnR���������낤�����̓��j�i�L�j�ɔ������܂��B
�����֑吨�̐_�l�������ʂ肪����A
�C���Őg�����Ċ������悤�ɂ����߂܂����B
��������Ƃ܂��܂��ɂ��Ȃ�܂����B
���炭���đ单�l�i�卑��_�j������Ă��āA�u�^���Ő���āA���̕�Ȃ�
�g������݂Ȃ����B�v�Ƃ����܂����B
�����ɂ�����A�ɂ��Ȃ��Ȃ��āA
���낤�����́A����ƈ��S���āA���邱�Ƃ��o���A
�V����������������������B
�ƌ������b���ɏo�Ă��鑐�ł��B
�@��̒��F�������͎��ԂŁA�Y�Ԃ͂��̐�ɂ��܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ʐ^�ł͌͂ꂽ�̂��݂��܂��j
�t�����N�t���g�\�[�Z�[�W�݂����Ȋ����ł��B
�ʖ��̃~�X�O�T�́A�t��s���炷�����ނ������������Ƃɂ��܂��B
���������H���[�܂�Ƃ��̒��F�����̕���Ȗтɕς��܂��B
�@�H�̎���
���̉ԂƂ����w�H�̎����x�̈�ł�
�H�̎����Ƃ́A�n�M �E�L�L���E �E�N�Y �E�i�f�V�R �E�I�o�i�i�X�X�L�̂��Ɓj �E

�I�~�i�G�V �E�t�W�o�J�}
�y�����S���Ғ��̎������z
�@�@�P��(�ق����j�����S���E���w���ԁA�k��15��
���сF���̉ԂƂ�����B�Ԏ��F�̉ԂŁA�����ɂ͂��̖F�����Y���܂��B
�@ ���R�Ɏ���E�̌@���R��������܂��B
�A�s����(�ӂǂ����j �����S���E���҉w���ԁA�k��20��
���q�F���q�̒W�g�F�̉Ԃ͗D������������������܂��B
�@ �{���̕s�������́A1�N��1�����肢��������ƕK�������Ă����
�@ �ƌ����A���s���̕ʖ�������܂��B
�B�^����(���傤���j�����S���E���w���ԁA�k��10��
���Y�ԁF�H�̎����̒��ň�ԑ����J�ԁB�N�₩�ȉ��F�������B
�@ �O�@��t��Ƃ����镧��t�@������A��3���N�O�̒����Ð��w���甭�����ꂽ�≎�Ȃǂ�
�@ ������܂��B
�C����(���ق����j�����S���E���w���ԁA�k��10��
�j�[�F���Ɣ��̋j�[�����������ɊJ�Ԃ���ƁA�������N�₩�ɍʂ��܂��B
�@ �{���͏\��ʊϐ�����F�ŁA���e�ɕs�������Ɣ�����V���J���Ă��܂��B
�D�����@�i�Ƃ����傤����j�����S���E���w���ԁA�k��20��
���F�R���E�����E���v�����ȂǑ����̕i�킪����A�����{���g�┒�̏����ȉԂ��炩���܂��B
�@ �{���͕s�������ŁA���̕ӂ�ł͒��������̉@������܂��B
�E�ՏƎ��i�ւ傤���j�����S���E���w���ԁA�k��40��
���F�t�ɖ�����Ď��F�̉Ԃ��炩���܂��B
�{���͖��s�Ґ_�ϑ��F�i����̂��傤���Ⴕ����ڂ��j�ŁA�ؐ���Â���̑�����
���u����Ă��܂��B�����E���ɂ͊��̃g���l��������A�Â������Y�킹�܂��B
�F�������i�ǂ��������j�����S���E����w���ԁA�k��10��
�@ ���ԁF�����F�̕䂪�H���ɐ�����Ĕg�ł��܂��B
�@ �{���͎߉ޔ@���ŁA�J��Ă���g�̏��ړ̑��͉^�c�̍�Ɠ`�����Ă��܂��B
�c���݂ɏt�̎����́A�Z���E �i�Y�i�i�y���y���O�T�j�E �S�M���E�i�n�n�R�O�T�j �E�n�R�x���i�n�R�x�j
�z�g�P�m�U�i���݂̃z�g�P�m�U�ł͂Ȃ��C�^�r���R���w���j �E�X�Y�i�i���j �E�X�Y�V���i�卪�j
�@
�@�V��
�@�{��9��15���͌h�V�̓��ł������̂ł��B
1951�N�Ɂy�Ƃ����̓��z�ƂȂ����B
�����āA1966�N�̍����j���@�����Łu�h�V�̓��v�ƂȂ�A
2003�N�̏j���@������9��15�����疈�N9���̑�3���j���ɕύX���ꂽ�B
�R���ɔ����A����܂ł̌h�V�̓����L�O���Ƃ��Ďc�����߂Ɂu�V�l�̓��v�Ɛ��肳�ꂽ�B
�����̊ԂɍL���V�l�̕����ɂ��Ă̊S�Ɨ�����[�߂�ƂƂ��ɁA
�V�l�ɑ�����̐����̌���ɓw�߂�ӗ~�𑣂����B
���̓���723�N�������q���l�V�����ɕn�����l��a�l�E�ǎ��Ȃǂ��~�ς���
�ߓc�@�i�Ђł�j��ݗ�������
�Ƃ���Ă��肻��Ɉ����̂ł���A�������j�����B
�����J���Ȃ́A�������ŕS�Έȏ�ɂȂ鍂��҂��P�����݂ł܂Ƃ߂āA
����17�N�́u�����ԕt�v�\�����B
����ɂ��ƁA�S���̕S�Έȏ�̂��N���͂X�������_�őO�N���2,600�l����25,568�l�ŁA
35�N�A���̉ߋ��ő����L�^�����B
�����҂̑������߂�̂͏����ŁA���߂ĂQ���l�̑���˔j���Ă����B
���n���Ō�ɐ����c��̂͏����c�@�փb�ւ�p(�P�[�P)q
�s���{���ʂŁA�l���\���l������ɕS�Έȏ�̍���҂���߂�䗦�́A
���ꌧ��51.43�l�ŏ��a48�N����A���g�b�v�B
���m�A�����A�F�{�A�������e���������A�����{�ɒ��������W�����A
�ł��Ⴂ�͉̂�A�ʂ̍��E���9.81�l�iT-T�j
�S�Έȏ�̍���҂͈�Â̐i���Ȃǂő��������Ă���A
���a56�N�ɂ͖���l���������A����10�N�ɂ͈ꖜ�l15�N�ɂ͓l��˔j�B
���ώ������A�����̏ꍇ�ŏ��a38�N��72.34���畽��16�N�ɂ�85.59�ւƉ��т��B
�����s�V�l�����������̔�����E���������́u50�N��̕��ώ�����90�A100�N���100�B
�����I�����ɐ��܂ꂽ�����́A�����I�܂Ő����邱�ƂɂȂ肻�����B�v�Ɨ\�����Ă���B
�ׁX�Ɓy�Ђ����̓��z�ł�����܂��B
�O���̂悤��9��15���Ƃ����̂́A�N���A�h�V�A�V�l�c�������̓��Ȃ̂��B
���{�Ђ�������A���N�H�i�w�Ђ����x�̔̔����i�ړI��
���u�h�V�̓��v�Ɉ��݁A�̂���w�Ђ�����H�ׂ�ƒ�����������x�ƌ����Ă��邱�Ƃɂ�萧��
�@�����̌ꌹ
�w�����x�͐́w�m�X�v�x�Ə����܂����B
����́@�@���_�V�c�i������Ă�̂��j�́@�A���i�݂�j��
�m�X�v�F���i�����ԂЂ��݂̂��Ɓj�����̒n�̍����i���ɂ݂̂���j��
�C�����ꂽ���炾�ƌ����܂��B
�m�X�v�F���́w�Î��L�x�ŗL���Ȕ��ӎv�����i�₲���남�������˂݂̂��Ɓj��
�\��̑��ɂ�������ł��B
�܂��A���̑��A�����n���Ɂw�����̖x�i�����傤�j�����Ă�������c�Ƃ�����������܂��B
�����傤�ɂ́A�}�̉��ɓ��[�̂悤�ɐ��ꉺ���邱�Ԃ�����܂��B
���̂��ߓ��̖c�܂肿���̖ƌĂԂ���ł��B
���ꂩ�璁���n���ɑ������i�ΊD��B���b�R�͂��̑�\�I�ȕ��ł��j����`�`�u
�ƌ������ƌ�����������܂��B
�c�����A�ǂ����́u�����v���u�ԁv�������ł���ˁB
�m�X�v�F���́A�������J�����剶�l�Ȃ̂ŁA�����_�Ђ��J���Ă��܂��B
���̌�A�a���N�ԂɂȂ�ƍ��̖��́u�������ɉ����v�̒B��������A
���̎�����m�X�v�𒁕��Ə����悤�ɂȂ��������ł��B
�N�����߂����m��Ȃ����A
���̎���̊����Œm�X�v��\�����w�����x�̎�����Ԕ����������������̂ł��˂��B
�����̋{�Ɠ��������Ȃ̂͂���т��ƋC�ɂȂ�Ƃ���ł��B
�@�L�I�ŁA��\��̓V�c�B�J���V�c�̍c�q�B
�A�V�c�̎����B�܂��A���݈̍ʊ��ԁB
�@�\�ܖ�
�@���H�̖����Ƃ͉A���8��15���̌����u�\�ܖ�v�u���H�̖����v�ȂǂƂ����܂��B
���N�͐V��9��18���ɂ�����܂��B
�A��ł�1�`3�����t�A4�`6�����āA7�`9�����H�A10�`12�����~�ł��B
������8���͏H�̒��̐^�̌��Ȃ̂Łu���H�v�ƌĂ��̂ł��B
�×��A���{�l�͌����߂łė��܂������A��͂薞������Ԕ��������̂Ƃ���܂����B
���̒��ł����H�̂��̎����͋�C������ł��āA�ł������������������Ƃ������ƂŁA
�������㏉���ɁA���̓��A�������Ȃ��牃������镗�K���ł����̂ł��B
���̉��͌������Ȃ���a�̂�ǂ݁A���̏o�����݂�Ȃŕ]���������Ď�������Ŋy���݂܂����B
���̍s�����蒅���n�߂�ƁA���̌����鏊�ɂ�����������A�����c�q�A�����A�}���Ȃǂ�A
��_����������悤�ɂȂ�܂��B
�V�C�̈����ꍇ�͏\�Z��(�����悢)�\����(�����܂�)�ȂǂɊ��҂��|���܂����B
���H�̖����Ƃ����̂́A�A��8��15���ŁA�܂�V������14����������킯�Ȃ̂ł����A
�V������14���o���Ă��邩��Ƃ����āA�K�����������ɂȂ�킯�ł͂���܂���B
�n�������z���ȉ~�O������]���Ă���̂ŕK���������̑��x�œ����킯�ł͂Ȃ��A
�X�ɂ͐V�����钆�̂O���W���X�g�ɋN�����̂ł���������A���̕��̃Y�����������ł��B
�����͒����̒��H�߂̉e���Ŏn�܂������̂Ƃ���܂��B
�����ł͌��݂����̓��H�ׂĂ����̂ł����A���{�ɗ���ƌ����c�q�ɕς���Ă��܂����悤�ł��B
�������A���̌��������Ԃɒ蒅����ɂ������ẮA��͂肻�̊�b�ƂȂ�K��������܂����B
���ꂪ����ՁA�܂�H�̎��n�Ղł���Ƃ���܂��B
�t�������|���Ĉ�Ă��앨���H�ɂ͎���A�l�X�ɑ厖�ȐH���������炵�Ă���܂��B
���{�l�͂��̎��R�̌b�݂Ɋ��ӂ��Ă��̎������낢��ȍՂ��s���܂����B
���ɂ��̎����ɑ����j��ꂽ�̂͗����̎��n�ŁA���̂��߁A�����ɗ����������镗�K���ł��A
���̖������u���������v�Ƃ��u�����̂��a���v�ƌĂԒn��������܂��B
���̈𖼌��̖�͐̂͑����̒n���ŁA
�l�̔��ɐA����Ă�������u����Ɏ���ĐH���Ă������v�Ƃ������K������܂����B
���������ł�����Ă����Ƃ�����ł͂Ȃ��u������Б����ݍ����܂łƂ���v
�Ƃ������ł����B����́w�Б���Ɓx�Ƃ������K�ł��B
�̂̓��{�Ƃ����̂́A���̂悤�ɓ���̓��ɂ݂�Ȃň������Ƃ����邱�Ƃ�F�߂āA
����ɂ���Ċe��̃X�g���X���������Ƃ����Љ�I�Ȏd�g�݂��ł��Ă��܂����B
�����悤�ȕ��K�̓��[���b�p�ł����\�N�O�܂ł͌����
�W�c�ŋ��𓐂�ł݂���A�n�Ԃ�̏�ɂ����Ă��܂�����A������ܒ@���ɂ�����A
���s���l�ɓD�𓊂�������A�ȂǂƂ��������Ƃ��J�[�j�o���̎��Ȃǂɂ�镗�K������܂����B
����͂����������X�g���X���U�̋@������͎̂�ҒB�ɂƂ��āA�s�K�Ȃ��Ƃ����m��܂���B
���\�ܖ�̂������i�Ւd�������炦��j
�\�ܖ�̂������͒n���ɂ���Ă��ꂼ��̂悤�ł����A
��{�́c��_���i���{���j�B
�@�@�@�@�@�@�X�X�L�Ȃǂ̏H�̑��B
�@�@�@�@�@�@��V����s�˂������c�q��15���O���ɐ���̂������ł��B
�@�@�@�@�@�@�V���̗����₳�܈��A�Ԃǂ��E���E�`�ȂǏH�ɏ{���}����ʕ������������܂��B
���_�k����n�܂����s���Ȃ̂ŁA������͂��������܂���B
���_�I�̂���ƂȂ�A�Y�ꂸ�_�I�ɂ����������B
�������A����Љ�A���ꂵ���l�����ɉƑ��̍D���ȏH�̖��o�𑵂��āA
�����l�ւ̂��������牺������͖������Ϗ܂��Ȃ���݂�ȂŔ����������������܂��傤�B
�@�c���̓�
�@���i�A���C�Ȃ��g���Ă��邠�Ȃ��̕c��
����͍��̐���ɂ���āA��߂�ꂽ�̂ł���܂����B
1870�N(����3�N)9��19���ːА����̂��߁A
�������z���ɂ���ʎs�����c���������Ƃ�������܂����B
�������A�s���͕c�����Ȃ��Ă��s���R���Ȃ��̂ŁA�c���𖼏�낤�Ƃ��܂���ł����B
1875�N(�����W�N)2��13���i�c������L�O���j
���ׂĂ̍��������i�c���j�𖼏�邱�Ƃ��`���Â����܂����B
����ȗ��A���Ȃ��̐�c�͂��̕c�����d����Ă����̂ł���܂��B�����炭�c
�c���āA���Ȃ��̕c���͑S���ʼn��ʁH
http://www2s.biglobe.ne.jp/~suzakihp/index40.html
�@�@�@�@�@��
�c���̏��ʂƑS������������܂��I
�@�����̓��c
��ԑ����́c�ӊO�Ȏ��ɃR�R�ʂ̍��E��ʂłV�T��
��ԏ��Ȃ��̂́c�ȁE�ȁE�Ȃ�Ɖ��ꌧ�V��
����E���C�̃C���[�W�̉���ł����A
�����ɂ�鐅���C�Ő���̓��ł��_�̔����������̂������ł��B
�@�g�c�̌ꌹ�E�R��
�@���݁A�x�m�R�͋x�Β��ł����A�͉̂��x�������Ă��܂����B
�ŋ߂ł́A�]�ˎ���̕�i�l�N�ɕ����āw��i�R�x���o���܂����B
��������̉i�ێO�N�ɂ��啬������A�[�̕x�m�g�c�͑傫�Ȕ�Q���܂����B
�x�m�g�c�̐l�X�́A���̒n�ł̐����Č�����ߒ����ֈڏZ���܂����B
�������A�̋��̕x�m�g�c���Y���ꂸ����̒n�ɓ������O��t���܂����B
�Ⴆ�A��g�c�E���g�c�E�ցE����E��̌��E��Ȃǂł��B
�i��͉������̍�̏�̒n�B�ցE����E��̌��͉������̓쐼�����H�J�i�j
�܂��A�x�m�R�Ɏ��Ă���R���w��ԎR�x(������)�Ɩ��t���āw�x�m��ԎЁx���J��܂����B
�@�J�}�M�b�`��
�m�荇���̂����u�J�}�M�b�`�����Łv����
�u�����J�}�L���˂��v���āA���Ă݂��
�����ɋ����̂́w�g�J�Q�x�ł����B
�u����H�J�}�M�b�`�����ăg�J�Q������������H�v
�����Œ��ׂĂ݂��Ƃ���
��z�⒁���ł́w�J�}�L���x�̎����w�J�}�M�b�`���x�ƌĂт܂����A
�Q�n�̕��ł́w�g�J�Q�x���w���悤�ł��B
���Ȃ̂ɓ������t����ނƍ����Ƃ́c�����Ėʔ����ł��ˁB
�@�u�����ށv���Ċ���
�]���āw�����ށx�̌ꌹ�́w�����݁x�ł��B
�y��́A�����߂���́E�d�˂�����́E�~�����ׂĂ��Ӗ��������̂ŁA���ꂪ��̋N����ł���B
�@�~���Ƃ��Ă̏�́A�w�Î��L�x�i712�N�j�Ɂu����v�u�������d�v�u������d�v�u���ʏ����d�v�̋L�^������܂��B
�u���{���L�v�i720�N�j�Ɂu���d�ȑE�v���A�u���t�W�v�ɂ��u�ؖȏ�v�u���d��v�u���E�v�Ƃ������������݂��܂��B
�@����i�X�Q�̗t��҂ނ���̗l�Ȃ��́j��є�ȂǁA���鎞��Q��Ƃ��ɉ��ɕ~�����̂ŁA
���̂悤�ȃ��������������̂ł͂Ȃ��A�~������d�ɂ��܂�d�˂����̂̑��̂ł������B
�@�Õ�����ȍ~�ɐQ���Ƃ��ď��������悤�ɂȂ�A����܂ł̓y�ԂƊ��Ƃ̊ȒP�ȏZ������̕ω��ɔ����A
���̏�̕~���Ƃ��Ă��̂悤�ȑE��⥂̂悤�ȏg����悤�ɂȂ�B�����̓x�b�h�̕~�z�c�̖��������Ă����B�z
�@���{���̓�
�V�ĂŎ���n�߂�̂�10���B
����\���u�сv�̎��͏\��x��10�ԖځB
����Ɂu�N�x�v��10��1������n��B
�����Ǝ��ɊW�̐[�����̓��𐴎���PR����u���{���̓��v�Ƃ��܂����B
�@���@����Ə��R
�G���͖��_�ЂɎQ�q���A�u���������߂炦���܂��悤�Ɂv�ƋF�����B
����ƁA���̔ӁA�l�Y�~�̑�Q�����R�ɉ��������A�Z�⊕�̕R�����ݐ��āA�g�����ɂȂ�Ȃ������B
�����ŏG���͈�C�ɏ��R�ɍU�ߓo�����B
�s�ӂ�˂��ꂽ����̌S�͗���A�⌊�ɉB��Ă���������߂炦��ꂽ�B
����͏G���̑O�Ɉ����o�����Ɓu����ł�����v�Ǝ��疼������B
�Ƃ��낪�����ē�����`�̏��傪�߂炦���u����ł�����v�Ɩ�������B
�G�����ڂ�������A�l������ł���ƁA�O�l�A�l�l�A�ܐl�c�Ȃ�Ɣ��l���̏��傪�߂炦���A
�u����ł�����v�Ɩ�������B
�����ֈ�l�̉Ɨ����A�Ⴂ����߂炦�Ă����B
����͏���̎����A�w�j�[�x�������B
�u����͂ǂꂾ�v �Ɛu�˂����A�j�[�͌�������܂܂������B
�u���܂��������ʂȂ�A���l�̎�𝛂˂�B�U�̏���������E�����A���܂��̌��S��v
�G���̌��t�ɁA�j�[�͊ϔO���A �u�H���̎��A���߂��݂���ԑ傫�������̂�����l�ł������܂��v�ƌ������B
�����A���l�̏���ɐH������点���B
���߂��݂���ԑ傫���������{���̏���́A���Ɏ��ł���鎖�ɂȂ����B
����͎��ł����O�ɁA �u�j�[����ǂ��ԍ炭�ȁv�ƌ����c�����B
�����̋j�[�́A����̌��ǂ��āA���疽�������B
�u�H�̎����@�����́@�Ԃ́@�j�[�͂Ȃ��炩�ʁv�ƌ����̂̒ʂ�A
���R�ɂ́A�����j�[�̉Ԃ͍炩�Ȃ��̂ł��B
�@����̎�
�@��t�ڂ̂���
�{��ɔR��������̎�́A��֕����オ�������Ǝv���ƁA
�������X�萺���グ�āA�G���Ɍ������Ăނ���Ԃ���Ă������B
������J�b�ƌ��J���A����U�藐�������܂����`���ɁA
�G���͋����Ȃ��āA��ڎU�ɓ����o�����B
�Ƃ��낪�A����̎�͏G���������瓦���Ă��A����Ԃ悤�Ɍ��ǂ������Ă����B
���R������I���Ă��A��͂܂��ǂ������ė����B
�g�c�̒��O��܂œ����A�����ƌ���U������Ǝ�͌����Ȃ������B
�������G���͈ꌬ�̒����ɔ�э��݁A�������]�����B
�����̔k���o���Ă��ꂽ�����A������G���́A �u�|�������������v �ƌ����āA
�܂�����o�����Ƃ������A
�u���ꂱ��A�����Ɨl�B����ȂɍQ�Ă˂��ŁA������t����ł����������v �ƌ������B
�G���́A�C�͋}�����̂́A��t�ڂ̒���������Ĉ��B
��t�ڂ̒������݂Ȃ���A�O������ƁA����̎X����グ�Ĕ��ł������B
�u�������������v �G���́A���ʼn��낵���B
�i�G������t�����ő���o���Ă�����A����̎�ɕ߂܂�Ƃ��낾�������j
����Ȃ��Ƃ������Ă���i�g�c�ł́H�j
�u��t���͉��N�������v �u�����͓�t���ނ��v �ƌ�����悤�ɂȂ�����!!
�@�����͂��̓��̓��
�@�ނ��`���A�́A���̐́B �R�̒J�Ԃ̈ꌬ�ƂɁ@���ꂳ��Ƃ��k���Z��ł������ƁB
���钩�A��ւ��ꂳ��Ɣk�����ۂ�ł�낤�Ƌ߂Â����B
�Ƃ̗l�q�����������āA����������Ƒ_���Ă��B
�u�ꂳ���@����(��������)����t���܂����v
�u�������@����͎|�������B��������ׂ��v
����ɂ͑�ւ��������B
�u���ցi��������j��ۂނƂ́I����͋������B�����悤�v �ƁA�R�Ɍ������Ĉ�ڎU�B
�������傱���傢�Ȏւ����Ǝւ��ԈႦ�����A�ł��ꂳ��Ƃ��k����͖��E�������܂����B
���ꂩ�璁���̔_�Ƃł́A�w�����͂��̓��̓��x���āA
���������ނ悤�ɂȂ��������ŁB
�@���l���̎R���Ƌe����
�@�ނ��`���ȁA���≺���i���������Ƃ����j�ɂ́A���l�̎R�����Z��ł����B
���l�́A���̓����w���l���x�ƌĂ�ŋ���Ă����B
������R�������́A�ʂ肩���������m�̎������S�Ă�������B
�Ƃ��낪�A
���m�͏������������A�����ɔ����������ׂȂ��爣��ނ悤�Ȗڂ��ŁA
��Ɉ������Ōo����������ƁA�R�������͐g�������o���Ȃ��Ȃ����B
�u���݂̍߂͋ɂ߂ďd���A�������ɐS�����߂�Ȃ畧�̎��߂�������悤�v
�@���ꂽ�R���́u���S����̂Œ�q�ɂ��ĉ������v�Ɨ��ނ�
���m�́u�e���̗��ŐS�g���q��𐴂߁A�ϐ���������肵�Ȃ����v
�ƌ����� �R�[�̊ω���������ŗ^�����B
�R���͂��̒n�Ɏ������āA���ϐ�����F�����J����
�w�e�����x�ƌĂсA���l�̈��S���F�肵���Ƃ��B
�@�w�e�����x�͉i�\12�N�i1569�j�b�㕐�c�R�́u�M���Ă��v�ɑ����A�Ď������B
��ꂽ�ω��O���́i���≺�ω��j�͂₪�č���̒������֗a����ꂽ���A
�������͎���ɋe�����i�D��33�ԁj�ƌĂ��悤�ɂȂ�A���������≺�ω����{���Ƃ����悤�ɂȂ����B
���ׁ̈A���������{���i�ꌩ�ω��j�͍���̒h�Ƃɗa�����A
�h��18����1�������őꌩ�ω�������肷��w����ω��x�̏K���ɂȂ����B
���≺�ω��̋��n�͔��l���̘[�ɂ���A�e���̐�͑傫�ȋ�ǂ̖̉��Ɉ�˂Ƃ��Č������Ă���B
��˂͏�����ʂ̑傫���Ő[��2m�ʂł����B
���[��10cm�ʂ����Ȃ��������̂��Y��ȁA���݂����N���o�Ă����B
�@��t�̂���
�@�]�ˎ���ɂȂ�ƒ����Ɋω��Q�������l�������Ă����B
�����ɂ͎��M�̂��鏄����A�D��32�Ԃ���33�ԋe�����֏��鍠�ɂ�
�������܂�A�ޑq�̑哿�@�����āu���ꂪ�e�������H�v
�Ɛq�˂��ɂ͂����Ȃ������������B
�u���₢��A�e�����͐��n������̍���̗�����B
�������̒����ŋx��ōs���������B�v
�ƁA���l�Ɍ����āA����͊F�A���̒����ɗ���������ƁB
���̒����͓��Z�̖�t�l�̑O�ɂ����āA���������������Ă������B
�o����邨���͑傻�����������A�O�@���ƌĂ�Ă����B
�u�O�@�l�̂����v�ŁA��ꂪ���܂���B�v�Ɩ��������̂ŁA
������t�~�������Ă��A�����ē�t�ڂ͏o���Ă���Ȃ������������B
������B�ω��l�ɂ��Q�肵�āA����̗��ŏh��������j��
�u���̖��ɉ���āA���������������ς����݂������̂��v�ƁA���Z�̕ӂ�܂ň����Ԃ�����
�Ƃ��낪�����͌������炸�A��������������邤���ɁA�Ƃ��Ƃ����ɖ����Ă��܂����B
�_�v�ɓ���q�˂�Ɓu�����́A�悭�����ԈႦ���Ŗ��r�i�߂��ǁj��ƌĂ�ł����B�v
�Ə��A����ւ̓��������Ă��ꂽ�B
����Ƃ̎��ŏh�ɖ߂�A��O�̋������ŁA�����̎���X��ɘb����
�u���߂��l�����ɖ������̂͊ω��l�̂��������B���̂������t������A�������Đg�̂Ɉ����B
�����ƍ������ɂȂ��Ƃ������B�v
���́w�O�@���x�ƌ�������
�w�J�����P�c���C�x�ƌ��������A�����������̂ŁA������鋭����̌��ʂ������������ł��B
�@�J�����P�c���C�ɂ���
�@�J�����P�c���C�i�}���ȁF�P�N���E����30�`60cm �E�Ԋ��V�`10���j
�J�����P�c���C�̖��O�̗R���́A
����������i���߂��E�G�r�X�O�T�j�Ɏ��Ă��āA�쌴�ɑ����������邱�Ƃ��炱�̖������܂����B�@�@�@�@�@�@
�s�t��E��Œ��̑�p�Ƃ��ČÂ�������p����w�O�@���x�ƌĂ�Ă��܂��B
���̑��ɂ��F�X�ȌĂі�������܂��B�t���l���m�L�Ɏ��Ă��āA�����̂悤�Ɉ��ނ��Ƃ���u�l���`���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��q���}���̂悤�Ɍ�����̂Łu�}���`���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�ӂ̎��n�ɑ����������邱�Ƃ���u�n�}�`���v��
���z����ꏊ�F�{�B�A�l���A��B�̓�������̂悢����A�͌��A���[�A�r�n�ɌQ���P�N���B
���������E�����F�s�͂�⌘���т�����A����ł͂���܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�͌ݐ����A�����H�t�ŁA���E�s�ύt�ɑ����̏��t�����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԃ�8�`10�����t�̘e�̏��}��1�`2�̉��F�����Ԃ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�a��7mm�A�ԕق͂T�قł��ꂼ��̉ԕق͂قړ��`�A�|���^���������ˏ�ԂŁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʓK�Ȓ��`�Ԃ�����}���ȐA����茴�n�I�Ȃ��̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y�����͂S�{����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʎ��͂���ʂŕ������A����3�`4cm�ŕ\�ʂɍזт������Ă��܂��B
�̏W�ƒ����F8�`9�����A�ԂƉʎ��������S�����̏W���A�����A
�@�@�@�@�@�@�@
���A�ɒ݂邵�āA2cm���̒����ɍ��݊��������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@ �����́A�R�Γ��i����j�Ƃ����܂��B
�� ���F���{���s�E���P��Ƃ��āE�r�C�E�t���E���t�E�Γ��ɁE�����֔�E ���A��p�E��ӏǁE�C���|�e���c�Ȃ�
���A��p�E��ӏǁE�C���|�e���c�Ȃ�
�p�����F���Ԗ�Ƃ��ẮA���A�A�ɉ�����x�ɂ��܂����A�P����20����
�@�@�@�@�@�����Ē��Ɠ����悤�ɂ��Ĉ��݂܂��B
�@�@�@
�@ �����u�����������݂₷���A�܂������ڂ�����܂��B
�@�@�@
���܂葽�ʂɕ��p����ƕ��ɂ≺�����N�������Ƃ�����܂��B
�ŋ߂̌��N���u�[���ŃJ�����P�c���C�����̈��Ƃ��ė��p����Ă��܂��B
�A���g���L�m���n�̐������ܗL����Ă��܂��̂ŁA�ɉ���p������܂��B
�G�r�X�O�T��n�u�\�E�̎�q�Ɠ��l�̖�������҂ł��܂��B
�@�T�����̂ق���
�@�����삩�痬�ꍞ�ԕ���́A���䋴����Ԍˋ��̊Ԃő傫���Ȃ����ė���Ă���B
�����ɂ͍����R�Ƒ傫�ȕ��������Ăȁw�y���x�ƌĂ�ł���B
��������T�O�O���ʉ����̐��ۂɁA���N�ق���������������A
�^�������Ă��A�y�����ꂪ�N���Ă��A�܂�������B
���S�N���̒����ԁA���������Ă���̂Łw�y���̎T�����̂ق����x�ƌ����Ă�����B
���́A�i�\�O�N�B���c�����E�k�����N�������ɐN���������̎��������B�y���̖V�ƌ����m�������āA
���̎�����E���c�M���ɂ��`�����˂�
��Ɋ����Ă�����ⴑ���͂ނƁA�����ڂɔn�𑖂点���B
�������A�����ɒx���A�G�͎�������͂�ł����B
�y���̖V�͓�����������āA�Ԍ˂̊R���畣�ɐg�𓊂��Ď���ł��܂����B
���̎��A�y���̖V���ڂɎg���Ă����ق������̎킪�ڂ��o���A
�����y���œy���̖V�̗�Ƌ��ɐ��������Ă���B
���̂ق������������A��Ɠy���̖V�̗삪�s�K�������炷�ƌ����Ă�Ƃ��c
���́A���̓y���B�䂪�Ƃ̂����߂��B
�q���̍��͉ď�ɂȂ�Ƃ����ŗǂ��V�B
���݂ł͐쐣���ς���Ă��邾�낤���A
���̍��͂P��50cm�͂���[�����ŋ����ǂ��߂ꂽ�B
�e���畣�̂����͕����Ă������A�ق������͌��������Ȃ��B
���e�̘b���ɂ��A�ق������͖��N�A�����Ă����i�ߔN��ݍH�����s��ꂽ����ǂ������j�Ƃ̎��B
�c�����A�ق������������A��ȁI�ƁA������ꂽ�L���͖����A�e���������������`���͒m��Ȃ��ƌ����Ă����B
���̎��G�Ȃ�͂ꂽ�ق��������c���Ă��邾�낤���猩���ɍs���Ă݂����A��������Ȃ������B
���݂́A�₦�Ă��܂��Ă���炵���B
�@�e�f�B�x�A�̓�
�@�A�����J��26��哝�̃Z�I�h�A�E���[�Y�x���g�́A���ŏ��F�ɂƂǂ߂̈ꔭ�����̂����₵�܂����B
���̃G�s�\�[�h�ɂ��Ȃ�ŁA�������ꂽ�F�̂ʂ�����݂��u�e�f�B�x�A�v�ł��B
���̖��O�͑哝�́u�Z�I�h�A�v�̈��́u�e�b�h�v����u�e�f�B�x�A�v�Ɩ��t�����܂����B
10��27���̓Z�I�h�A�E���[�Y�x���g�̒a�����ł��B
���f�B�Y�j�[�A�j���@���܂̃v�[����̒a����
�@�@�v�[�ɂ͂R�̒a����������ƌ����Ă��܂��B
�@�����̒a�����F�v�[�́A�N���X�g�t�@�[���r�����P�̎��Ƀ~�������v���[���g�����u�e�f�B��x�A�v�Ȃ̂ł��B
�@�@�N���X�g�t�@�[���r�����a�������̂́A1920�N8��21���ł��̂ŁA1921�N8��21�����a�����ƂȂ�܂��B
�A����̏o�œ��F�͂��߂Ė{�̐��E�Ƀv�[���a�����������
�@�@����́A����́u�N�}�̃v�[����v���o�ł��ꂽ���ł��B
�@�@���������āA���s���ꂽ10��14�����a�����ƂȂ�܂��B
�B�f�B�Y�j�[�̒a�����F����̓f�B�Y�j�[�A�j���u���܂̃v�[����v�̃v�[����
�@�@�X�N���[���Ƀf�r���[������
�ł��B
�@�@�f�悪���J���ꂽ2��4�����a�����ƂȂ�܂��B
���f�B�Y�j�[�ɂ�����u�a�����v�Ƃ�
�t�@���̊Ԃł́u�X�N���[���f�r���[�̓����a�����v�Ƃ����l�����Z�����Ă��܂��B
�����ɒa�������ݒ肳��Ă���u�~�b�L�[�i11/18�j�v�Ɓu�h�i���h�i6/9�j�v�̒a������
�u�X�N���[���f�r���[�̓��v
������ł��B
���L�����N�^�[�ɂ͌����Ȓa�����͂���܂��A���a�������N�Ƃ����͔̂��\����Ă��܂��B
����̓X�N���[���Ƀf�r���[�����N���琔�����Ă��܂��̂ŁA
��͂�u�a�����v�Ƃ����̂̓X�N���[���Ƀf�r���[�������ƍl������������̂ł��B
�@�����g�t���
�@��R�X���X��11�����{�܂�
�y�������z�@�@�����`�����������A����������ٍ��܁B
�@�@�@�@�@�@�@�@����f�����[�g�ɗאڂ���I�c�̋x�k�c1.2ha�𗘗p
�@�@�@�@�@�@�@�@���b�R��w�i�ɐF�Ƃ�ǂ�̃R�X���X���炫�����B�i�ǂ̐A�̓u���b�N�ɂ̓x�S�j�A�̉Ԃ�
��g�t��10�����{�`11�����{
�y���_�z�@���̗l�Ȍ`�������W��1724m�̗��_�R�����V�I�c�c�W�E�i�i�J�}�h�����R����l�ȐF�����Ő��߂�
�@�@�@�@�@
�ې_�̑�⏸���̑�Ȃǂ�����A���ꂽ���ɂ́A�R������_��R���������A�R���]�߂�
�@�@�@�@�@
���A�艷��u��t�̓��v�����h�Ɂu���_���v������
�y���E���Ìk�z�@����n��`���Ð�n��܂�10km��������ǂ����E���E�i�i�J�}�h�����ъG�����o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���A���ꉷ��u�V���فv�≷�������A���u����X�^���h�v������
�y��ꥎO��R�z�@�O��R�̖��͖��@���x�E����R�E�_��R�̎O�R���ނ��鎖�Ɉ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���[�v�E�F�C����̒��߂��f���炵��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���ɂ͓��{�����̑n���Ɠ`������O���_�Ђ�����
�y��꥓��đ�z�@���g���l����ڕW�ɍs���A���ċ���O200m�ʂ̒n�_����Ԃ����ċ��Ɖ��F�����勴�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�R����g�t����]�ł���
�@�@�@�@11�����{�`���{
�y���ҥ���z�@�����Њ₪�܂�d�Ȃ���̏��̉��t
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԥ��E���F�̖X�ōʂ�Ί݂̊ݕǂƏH��̐�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@12���`27���͌��̐��݂���(��ʎ��R�j�����ٕt��)
�@���v�����X���܂Ń��C�g�A�b�v
�@�@�@�@�@�@�@�@ �ŏI���ɂ̓~�j�R���T�[�g�J�Ái�J�V���~�j
��~����11����{�`12�����{
�y�����쒬�ѓc�z�@�D��31�Ԋω��@��O�A�n�����O(�y�Y�E�H����)��a��E�R�c�ƊǗ��́u���ؓ��̍��R�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@11�����{�ɂ͍g�t���y���߂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(��������250)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��X�~��12�����{�`2�����{
�y���ҁz�@��o�R�~�S�ԉ��E���E�o�C���ɂӂ������ƍ炭1500�{�̉��F���ԁ@�@�@�@�@
�@�����̌|�\�l�E�L���l
�щƂ�����(�����)�F�����N�Ȃ�ł�����ƒm�荇���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^�ł��Ɛ��������݂ł���Ղ�ɂ͖��N�Q������钁��������Ȃ�������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C��炸�A�̂��炸�ڂ��Ă����ǂ��l�ł���O�O
�ꐡ�@�t(�̎�)�F�����̓������B�Ⴂ�ޓ��A�v�X�̊��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�߂��Ń��C�u�̎��ɂ͖��B������(���)�s���Ă��܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�Ȃ��q�b�g���ĐF���TV�ԑg�ɏo���ł���悤�������Ă��܂�
���䌫(THE
ALFEE�����o�[)�F���ꂷ���Ēn���ł̃R���T�[�g�͓���Ƃ��B�c�O�ł�
��������(�o�D)�F���߂Č����̂�吐�K�j����̕���ł���
�@
�ŋ߂͂��Ȃ�ǂ��������������Ă�����Ă��܂����
����Y(�̎�)�F���́B�������ނ̉̂Ȃǁc
���ؖ��(���p�]�_�Ɓj�F�����Ă݂͂����̂́c���̐l�A�N�H
�c�㖾(�v�����X���[)�F10�N�O�ʂɋ߂��̎���Ŗ�����̌��������s��ꂽ�炵��
�����o�g�ł͂���܂���
�x�k�^��(���D)�F�ޏ��̕�(������)�͒����o�g�B��������Ƃ͌��\���ǂ�������ł�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�X�J�E�g���ꂽ�����ŁACM�ETV�E�f��ƈ������肾���I
�����|��(���D�j�F�����S�s���ɂ��Z�܂��ł��B�X�[�p�[�ł�����鎖���c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�v���C�x�[�g�ɂ��ւ�炸�A�ۂȊ�����鎖�����A����ɂ������Ă��������܂���
�n粂������낤(��ƁE�G�{���)�F�g�c�ݒ��B���Ƌ߂��ɂ��Z�܂��ł�
�����āA���Љ��������������O���I
�_�R����Y(�f��ē�)�F�f�梑��̗������
���c�F�I(����)�F�f�梑��̗������l�E�^�����`��o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�{����莟���(�{�l�ł��番��Ȃ��f��)�ɃN�����N�C��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
������ɂ��z���̎��ɂ͉�X�ɂ�������肭�����袓`����[�߂�������オ���Ă�����܂�
�@
�@�`����[�߂H�ׂȂ����TV���p���̂�����ׂ�͂ƂĂ��y�����ł���I
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�F�l�ɂ����������������V�[���ł��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�˖{�A��(�f��ē�)�F�f�梒��M�A���Q���S�[�X�g�l�S�V�G�C�^�[�����BTV��h���S��������o�c�Ɗ������I
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��X�ɂ����z�������܂����B�����āA�J���I�P�ցc
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Â��ȕ��ł����A�C�����b�̂ł�����ł��O�O
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f��D���̎��Ƃ��ẮA����삪�҂��������ƌ������Ƃ���I
�@11��25���i���j�̋L��
�@�����Ƃ́c
���ׁ̈A���Ă͑�{��(�����݂₲��)�ƌĂ�A�����̖���1915�N�܂ł͑�{��(�����݂�܂��j�ł������B
�����ɂ͎��R�����^��������オ�钆�ŁA�o�ϕs���̒����_���������n���ŕ����I�N����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(���������j
1889�N(����22�j 4�� 1��- �������{�s�ɔ����A�����S��{���E�ʏ������������A��{���ƂȂ�B
1916�N(�吳5)�@ 1�� 1��- ��{����������ύX���A�������ƂȂ�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����́A�����S�̒��S�ɂ��鎖�̑���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1914�N�ɊJ�Ƃ��������S���̉w���S�����̂��āu�����w�v�ƂȂ�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �������̖k�����S��{���i��̑�{�s�A���݂̂������s��{��Ӂj
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ̍����������ׂȂǂ����R�Ƃ��Ă������ƍl������B
1950�N(���a25) 4�� 1��- �s���{�s�ɂ��A�����s�ƂȂ�B
1954�N(���a29�j 5�� 3��- �����S���J���E���c������ғ�����B
1954�N(���a29�j11�� 3��- �����S�v�ߑ���ғ�����B
1957�N(���a32�j 5�� 3��- �����S��c����ғ�����B
1958�N(���a33) 5��31��- �����S�e�X����ғ�����B
2005�N(����17) 4�� 1��- �����S�g�c���E�r�쑺�E��ꑺ�ƍ������A�����s�ƂȂ�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�V�E�����s�̎s��-��������@�s��-�������@�s��-������)�@
�@12��1���i�j�̋L��
�@�f��̓�
1896�i����29�j�N11��25���@�G�W�\�������������L�l�g�X�R�[�v���g���āA
�_�˂œ��{���̉f��̈�ʌ��J���J�n����A
���̉�����̂���̂��������L�O���Ƃ��������ł��B
�@12��2���i���j�̋L��
�@���{�l���̉F����s
TBS�̏H�R�L���L��(����)���ڂ����\�A�̃\���[�YTM11�����ł��グ���A
���{�l���̉F����s�ɐ������܂����B
�@12��3���i�y�j�̋L��
�@������ՁB�����āc
�@�J�����_�[�̓�
�S���c���q�J�����_�[���c�1987(���a62)�N�ɐ���B
1872(����5)�N12��3�������z��̗̍p�ɂ����1873(����6)�N1��1���ƂȂ�܂����B
�@�����ԓd�b�̓��C�R�[�h���X�d�b�̓�
1979(���a54)�N�A�d�d���Ђ�����23��ł̎����ԓd�b�T�[�r�X�ƃR�[�h���X�d�b�̃T�[�r�X���J�n���܂����B
�����̃R�[�h���X�d�b�́A�d�g�@�̋K��ɂ��d�d���Ђ���݂̑��o���݂̂Œ���Ă��܂����B
���݂̂悤�Ɏ��R�ɔ���肪�ł���悤�ɂȂ����̂�1987(���a62)�N10������ł��B
�g�ѓd�b��1987(���a62)�N4��10������T�[�r�X���J�n����܂����B
�@�Ȃ̓�
�ʔň����1995(����7)�N�ɐ���B
���ӂ�\���u�T��(3)�N�X�v(Thanks)�̌�C�����B
1�N�̍Ō�̌��ł���12���ɁA1�N�Ԃ̘J���˂��炢�ȂɊ��ӂ�����B
�@�v���}�}�̓�
�x�r�[�������X�u�x�r�[�U��X�v�̍�����1���X�A�V�Y���X�̊J�X����12��3���ł��鎖�ƁA
12��3�����u�����ɂ�Ղ���v�Ɠǂތ�C���킹����A���{�g�C�U��X������Ђ����肵���B
�@���a����
�����ȍ~�A���m�����ƂƂ��ɃL���X�g���̊T�O������ɂ�A���N�̒a�������j���悤�ɂȂ�܂����B
��1�̏��a�����������j���Ă�������́A
�a�����ɖ݂����A���_�ɂ��Q������āA����ȏj�����J���Ƃ����̂���ʓI�Ȃ��̂ł����B
�@�a�����ȑO�ɕ����������q���ɂ́A�ꏡ�݂�w���킹�Ă킴�Ɠ]���A�Ƃ𑁂��o�Ă��܂�Ȃ��悤�ɁA
���ɕ����o���Ȃ������q���ɂ́A���݂�w���킹�Č��N���F��Ƃ����K��������܂����B
�w�O���̏K���x
���A�t���J������~�����}�[���͂��߁A�a�������̂悤�ɏj�����K�̂��鍑�X�����Ȃ�����܂���B
�܂��h�C�c��X�C�X�̂悤�ɁA���N�̒a�������ƂɐA���������Ȃ��K������������������܂��B
�L���X�g���Љ�(���ɃA�����J)�ł́A�a�����̓x�ɔN��̂낤�������o�[�X�f�[�P�[�L�ɗ��āA
������ꑧ�Ő��������Ɗ肢���������Ƃ��������`��������A���E���ɍL�܂�܂����B
�@12��6���i�j�̋L��
�@�����āc
���D�̏ꍇ�͓\�肠�킹��Α��v�Ȃ̂����A���͂����ƊȒP�ł���B
�j�ꂽ�����������茔���Ɗm�F�ł���悢�̂������ł��B
�ƌ������́c
�����̎�ށA�扽�A�g�ݔԍ��A������ԍ����c���Ă���ΊG���̕����͖����Ă������B
���������̋t�Ɂc
�N�V���N�V���ɂȂ��Đ������m�F�ł��Ȃ��ƁA�j��Ă��Ȃ��Ă������ɂȂ��Ă��܂������ł��B
�@�N���X�}�X�c���[�̓�
�@1886(����19)�N�̂��̓��A���l�ŊO���l�D���̂��߂ɓ��{���̃N���X�}�X�c���[�������܂����B
�܂��A���{�ŏ��߂ăN���X�}�X�̂��j�����s��ꂽ�̂́A
1875(����8)�N���A�������i�͂�
���˂����j���ݗ����������w�Z���ƌ����Ă��܂��B
�@12��8���i�j�̋L��
�@���u���V�����̓�
�ѐ悪�L���炸�A�܂����܂��g�������Ɍ����Ă��A�u���V�̒e�͎͂キ�Ȃ��Ă��邻���ł��B
�����Ŗ����W�������̓��Ǝ��u���V�����̓��Ƃ��āA1997(����9)�N�ɃT���X�^�[�����肵�܂����B
�@���ɂ�h���g�������^���h
�����u�C�^�^�v�ƂȂ������A�����Ƃ��Č��ɔ���Ԃ肽���Ȃ�B
���ꂪ��Ȃ������ŁA���܂��̋ؓ��֕��S���|����A���ɂ̌����ƂȂ�̂��ƌ����B
�m�炸���ɂ���Ă��邵�������B
����Ȏ��́A�t�ɑO���݂ɂȂ�A�[�������V������悤�ȉ^����2�`3��Ԃ��������ʗL��B
����܂ő����Ă����ؓ��̓����ɒ�R�Ȃ��������铮�������Ă���g���N������
�ɂ݂����Ȃ������ł���̂������ł��B
�@12��22���i�j�̋L��
�@�~��
�@�~���Ƃ́A��N���ōł������Z���A�邪�������ł��B
���z�̏��鍂�����Ⴂ�ׁA�e����Ԓ����Ȃ�܂��B
�~���͔N�ɂ���ē�������܂��B
���̓��́A���ڂ����H�ׂ���A�䂸���ɓ���܂����A
���ڂ���Ƃ䂸�́A���z�̏ے��Ƃ������Ă��܂��B
���̕ӂł́A���ڂ����H�ׂāA�䂸���ɓ���ƕ��ׂ��Ђ��Ȃ��ƌ����܂��B
�@�N���̎n�܂�
�����ɂ��Ɓu���{�v��11���I���A
�莆�̖͔͕��Ɂu�N�n�̂��������܂��v�����߂��Ă���B
�莆�͔�r�Ȃǂʼn^��Ă����B
���n�K�L�Łu�N���v���o�������悤�ɂȂ����̂͂��H
1873�N�i����6�N�j�ɗX�փn�K�L�����߂Ĕ��s����A
�ȒP�ɋC������`������@�Ƃ��āu�n�K�L�v���L�����p���ꂽ�B
���̍����瓯���Ɂu�N���v�����y�����B
���N���u�N���v���n�߂��̂��H
�w�N���x�́u�������ȒP�ɓ`���鎖�̏o����֗��ȕ��@�v�ƍl������
���R�Ɏn�܂����̂œ���̐l�͂��Ȃ��B
���u���N�ʂ����t���̔N��n�K�L�v�͂�����H
���a24�N�i���j��12�����甭�s���ꂽ�B
���̓����̈ꓙ�ܕi�́w�~�V���x�I�I�F�����ꂽ���i�������悤�ł��B
���N�Ԃ́u�X�֎戵���ʁv�́A�������ł������I
�N��270���ʂ̂����A�N���͂��悻40���ʁB
��l40���قǔN���������Ă��鎖�ɂȂ�܂��B
�@��������
�����������}����A�C�e����
��������
�������̗R���́A�������Ċۂ��A�����d��ꂽ���Ɏ��Ă��邩��Ƃ�����������܂��B
�������̏���͂��ꂼ��Ӗ�������A����(�V�_�A��)�͢�����ƕv�w�~����A�䂸��t�͢�ƌn���₦�Ȃ���A���z�͢��낱�ԣ�ɒʂ��A��͢��X�h����
�������p�̖݂���28���܂łɍς܂���̂��K�킵�ł��B
29����9���g��h�ɂȂ��炦�A�w������x����Ɣ������̂ł��B
�����ߓ�
���ߓ�́A�_�������鐳��ȏꏊ��\����ł��B
�������́A�Ƃ𐴂߂Ă����ɔN�_�l���}����ׁA��O�⌺�֑O�ɂ��̂��ߓ��悤�ɂȂ�܂����B
���叼
�叼�����镗�K�͒������N���Ƃ���A���{�ł͕������ォ���
���Ȃǂ̏�Ύ��͐_�l���h��Ƃ��A�Ƃ̖���ɂ��̐_���Ȗ̎}�𗧂Ă܂����B
�����āA�N�_�l�͂����`���č~�Ղ���ƐM�����Ă��܂����B���ꂪ�叼�̋N����ł��B
�叼�́A1�͎����ƗY������Ȃ�A�t���Z���čׂ��̂������B����������ĉE�ɏ���̂����܂�ł��B
���̖叼��29���ɏ���Ɓu�ꏼ�v���w�ꂪ�҂x�ƂȂ艏�N���ǂ��Ȃ��ƌ����܂��B
�����܂ł���ʓI�Ȑ�������̂悤�ł����A
�����n���ł́A���̑��ɐ_�I�̑O(�������ĉE����)�Ɂw�v�X�A�ɐ��A�@���ɂ��A��낱�сA�����A����A�x�ƌ����āA
����i�e�j�A��@���i�����j�A����߃C�J�A���z�A�����`�A�I�A�݂���(�{)���݂邵�܂��B
�ǂ̂����������26���`28���܂łɏ���܂��B
28���́w���L����ʼn��N���ǂ��x�ƌ����܂��B
29�����ǂ��Ȃ��̂͐�ɏ������ʂ�A
31���ɏ���̂͐_�l�Ɍ}����̂Ɏ���ȁw������x�Ƃ���܂��B
30��������ł͑�A���ɂ�����̂�31���Ɠ����Ӗ��Ł~�ł��B
�����J��
���݂́u����v�Ƃ͌��킸�u�J���v�ƌ����܂��B
���̋��݂��J���ĐH�ׂ�u���J���v��1��11���ɍs���̂���ʐ_���ł��B
���݂͐n���ł͐炸�A��܂��͒ƂŊJ���܂��B
���ǂ�ǏĂ�
�叼�₵�ߏ���Ȃǂ��������ʂ����i�X����������15���Ɏ�������Ă������グ����s���B
�u�ǂ�ǏĂ��v�̉��ɏ���ĔN�_�l�����A��ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B
���̋߂��ł́A�����s��g�c��g���ōs���Ă��܂��B